新井紀子さんは,NetCommonsを開発したときの,NIIのリーダでもある。NetCommonsは“LMS (Learning Management System)でCMS機能も統合したもの”という紹介の仕方でいいのだろうか。OSSコンソーシアムの教育ICT部会の活動のターゲットのひとつになっている。
(書籍出版元) https://store.toyokeizai.net/books/9784492762394/
(オーディオブック) https://audiobook.jp/product/240051
【まとめコメント】
この本の超サマリを私なりにすると2点。- 【AIに対して】AIを正しく理解しよう。ちゃんと理解していれば「シンギュラリティが云々」と不安がることもない。
- 【人に対して】問題は人の側。機械的なデータ処理にも劣る程度の理解力を改善しないといけない。タイトルは“教科書を読めない子供たち”だが、子供だけの問題ではない。
新井さんの関心事は,AIの方では無くて,人(教育)の方にある様だが,最初からそういう観点で東ロボ君のプロジェクトを進めていたのかどうかは未知数。勝手な邪推だが,途中から関心事が移ろっていたのでは?という感想をいだく。
ただ,TEDに登場したときの話と一貫しているのも事実。
→ TEDTalks テクノロジー 「ロボットは大学入試に合格できるか? | Noriko Arai」, http://www.ted-ja.com/2017/09/noriko-arai-can-robot-pass-university.html
【ピックアップ】 ((正確に引用しているわけではない))
- センター入試英語の穴埋め問題の簡単な状況を,東ロボ君は理解できなかった。
- … AIは「理解をしない」,「データを処理しているだけだ」。
- 統計が論理的に何を意味するのか解明されているとは言いがたい。
- … 見方によっては当然のこと。たとえば「平均値の意味」を統計学は与えてくれない。意味を持たせるのは統計学ではなくて,その値を使う側の責任。
- {前置き} AIが社会に与える影響を考えときの観点になる経済用語:
(1)一物一価,
(2)情報の非対称性 {売り手のみが詳しい情報を持っている様なケース},
(3)需要と供給の関係 - → これまでは情報の非対称性が続く期間は独占性によって利益を確保してきた/その利益が製品開発や品質向上に掛けるコストになってきた/けれどデジタル(≒インターネット)によって一物一価に至る時間が極めて短くなった/云々
- … OSSの普及や啓蒙の参考として興味深い。「情報の非対称性」の観点は,よく話題に上る。この論点(OSSと情報の非対称性)については,別途どこかで論じたい。
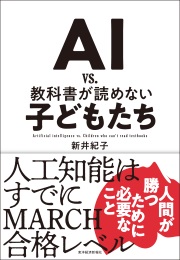
コメント
コメントを投稿